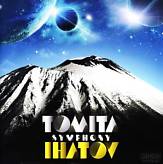 |
Hybrid SACD
2013年
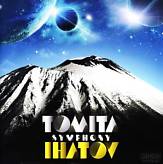 |
冨田氏のオーケストラ作品。ステージで演奏される大規模な新作としては、1998年の源氏物語交響絵巻以来ではないでしょうか。私もチケットを手に入れ、2012年11月23日、東京・初台へ、初演を聞きに出かけました。
コンサートの第1部では、冨田勲作品のいくつかが演奏され、山田洋次監督作品の映画音楽特集(山田洋次さんも会場に来ていて、紹介されていました)や、ジャングル大帝の音楽、そして大河ドラマ「勝海舟」のテーマ音楽が演奏されていました。
どの曲もすばらしかったのですが、特に勝海舟の音楽が圧巻で、かなり興奮して聞いていた記憶があります。
第2部に、「お待ちかね」のイーハトーヴ交響曲が演奏されました。演奏前には指揮の大友直人さん・そして冨田勲さんの解説もありました。
演奏中は、夢の中に迷い込んでしまったようなこの作品にとにかく大変感動し、演奏終了時は放心状態。内容が濃すぎて脳みそもオーバーフロー。
感動的で、奇妙で、壮大で、ちょっと変で。これはなんと表現したら良いのだ。こんな音楽今まで聞いたことがない。
冨田さんは、2011年11月頃NHKで放送された宮沢賢治関連の番組の中で、宮沢賢治をテーマにした新しい交響曲を構想中と言っていました。初演の1年以上前です。その後初演が決まり、チケットが発売開始になった際も、まだボーカロイド「初音ミク」起用は発表されていませんでした。私がチケットを購入したとき(2012年8月)も、まだボーカロイド起用の話はなく、発表は9月頃だったでしょうか。冨田さんは、「クローズアップ現代」で初音ミクを見てからボーカロイド起用を決めたと言っていましたので、それまでは、普通の合唱付きオーケストラ作品として作曲を進めていたと思われます。
映像付きのボーカロイドを、指揮者に合わせて歌って躍らせるなんて世界初の試みで、もしかすると成功しないかもしれないため、実現のメドが立つまで初音ミク起用は発表を控えておいたのかも知れませんね。(最悪ボーカロイドなしも考えていたのかも。)
ちなみに、私は「初音ミク」起用を発表する前にすでにチケットを購入済みでしたが、発表後は急にチケット入手困難になってしまったとか。
この作品ボーカロイドいらないだろ、という意見もありますが、これはシンセサイザー登場時によく言われた議論と同じで、人が生演奏したほうが絶対簡単なところをわざわざ機械でやるのに意味があると思います。(写真があるのだから絵画は無意味だ、という意見と同じになってしまう。)
曲について
岩手山の大鷲<種山ヶ原の牧歌>
児童合唱による、宮沢賢治作詞作曲の「種山ヶ原の牧歌」に続き、フランスの作曲家ヴァンサン・ダンディ作曲の「フランス山人の歌による交響曲」第1楽章のテーマが続きます。この「種山ヶ原」と「ダンディ」の旋律は、実に似ていて、このイーハトーヴ交響曲でもなんの違和感もなくつながっています。賢治自身も、フランスの牧歌を実際に聞いて、影響を受けているのかなぁ、と感じます。
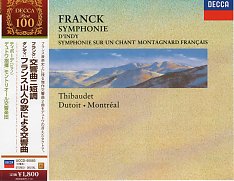 CD
フランス山人の歌による交響曲ほか。デュトワ指揮 モントリオール交響楽団
CD
フランス山人の歌による交響曲ほか。デュトワ指揮 モントリオール交響楽団
ちなみに、私の持っているCDの解説によると、ダンディは1886年の夏に、フランス中部山岳地方セヴェンヌの山々を望む土地ペリエで、耳にした牧歌に基づいて「フランス山人の歌による交響曲」を着想されたとの事です。
剣舞/星めぐりの歌
曲前半は宮沢賢治の「原体剣舞連」の引用だそうです。「夜風とどろきひのきはみだれ」からの旋律は、「フランス山人・・・」の第3楽章からの引用。これも違和感なくつながっている。
そして、賢治作詞作曲の「星めぐりの歌」が続く。
注文の多い料理店
重々しい弦から始まり、ハープとピアノが何かを暗示するような旋律を奏でたあと、主役のボーカロイドが登場する。チャップリン風という意見もありますが、これはヴァンサン・ダンディの「フランス山人の歌による交響曲・第2楽章」に出てくる旋律です。ということは、もともとはフランスの牧歌ですね。「アブラカダブラ〜」からは冨田氏の旋律でしょうか。
風の又三郎
激しい嵐を表現するのは、普通早いテンポにするのですが(たとえばベートーヴェンの田園・第4楽章や、ヴィヴァルディ四季の夏・第3楽章など。)この作品は、大変ゆったりとしたテンポのなかに、細かい音符をぎっしりと詰め込んで嵐を表現し、それが嵐の怖さ、不気味さを見事に表現しています。力強く地鳴りのように「どっどどどどー」と歌う男性コーラス、悲鳴にも似た女性コーラスが嵐の不安感を強調します。そして細かく動く弦。次第に風雨が強まることが感じらます。その中に突風が吹きぬけるようなハープが。低音弦のピチカートや高音弦と木管楽器のスタッカートは心臓の鼓動を表しているよう。
 映画「風の又三郎」のサウンドトラックCD
映画「風の又三郎」のサウンドトラックCD
「ドードドドドー」の旋律は、冨田さんが衝撃を受けたという1940年の映画「風の又三郎」(監督 島耕二)で杉原泰蔵が作曲した旋律だそうです。その後1956年村山新治監督により再映画化された際も、この旋律が使われたそうです。
さらに、冨田氏が音楽を担当した、1989年の「風の又三郎-ガラスのマント-」にも、冨田氏は杉原泰蔵のメロディーを起用し、そして今回のイーハトーヴ交響曲へも受け継がれたのですね。
初演は11月も終わる時期ということで、初音ミクさんはこの曲では冬の衣装で歌っていたようですが、会場での私の席は後ろのほうだったため、その時はわからなかった。
銀河鉄道の夜
この作品のハイライト。(と感じる)
「銀河鉄道の夜」というテーマでは、冨田氏は「月の光」を発表する前に、「試作品」としてシンセサイザーによる組曲として製作している。「冨田勲の世界」というレコードの中に収録されてはいるが、正式に作品としては発表されてはいません。
さて、 初音ミクが歌うこのワルツ調のメロディーは、「風の又三郎-ガラスのマント-」にもたくさん使われている旋律です。「サーカス小屋のオルガン」などに効果的に使われています。
ラフマニノフの引用もありますね。
曲後半「いつなのかわかりませんが」からは、賛美歌が元になっているらしいです。
会場では、ステージの背景・パイプオルガンに映し出された星々が幻想的な雰囲気を演出していました。
雨にも負けず
NHKの番組で放送されていましたが、この交響曲は、この曲が発端となっているそうです。冨田氏の旧友西澤潤一氏が、10年前に宮沢賢治の「雨ニモマケズ」に曲をつけてくれ、と依頼したそうです。無伴奏の混声合唱のみで演奏されます。心の奥の思いを表しているようです。
この曲なしに、今回のイーハトーヴ交響曲はなかったのですね。
岩手山の大鷲<種山ヶ原の牧歌>
静かにゆっくりと曲を締めくくります。ちょっと名残惜しいけど、物語は終わったのだなと感じる曲です。
アンコール
リボンの騎士
手塚治虫のアニメ「リボンの騎士」のテーマソング。手塚さんが存命なら、どのような感想を持ったのだろう。「アトム」にも描かれた、人間と科学の調和が今ここにある。
なお会場には娘さんの手塚ルミ子さんも来ていたそうです。
青い地球は誰のもの
曲のすばらしさは言うまでもないのですが、歌詞が「青い地球は誰のもの、誰のもの」と繰り返し繰り返し、問いかけているだけのものです。それだけになおさら印象に深く残ります。聞いた人それぞれに考えて欲しい、という願いが込められているのでしょうか。コンサートの締めくくりにふさわしい曲でした。